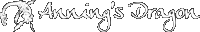インディ・ジョーンズ 剣山の秘宝〈第1話〉
・プロローグ
- 1274年 文永の役 -
蒙古軍は九州の北岸沖に、無数の艦隊を展開していた。
湾から見える海は船団で、埋め尽くされていた。
殺戮の限りを尽くし、敵を圧倒した後の一時の休息。
蒙古軍は激しい上陸戦の末、日本軍を押し込みつつあった。
一方で彼ら自身も大きな損害を受け、
艦隊は翌日の再編に備えて静かに停泊していた。
波ひとつない静かな海に雨がさんさんと降っていた。
その瞬間だった。
甲板を叩いていた雨粒が止まった。
時間が止まったのではない。
“音”が、世界から抜け落ちたのだ。
蒙古の将軍が見上げると、雲の裂け目に青白い光が浮かんでいた。
稲妻とも違う。
星でもない。
ただ、そこに“在る”としか形容できぬ光。
海は深く息を吸い込むように凪ぎ、
次の瞬間——
光が落ちた。
海面が、消えた。
爆発でも津波でもない。
世界から一枚の布を引き剥がすように、
蒙古の大船が、
小舟が、
艦隊の影が、
スン、と音もなく吸い込まれていく。
悲鳴を上げる暇すらなかった。
船体がきしむ音もなく、
炎も煙も出ず、
ただ青白い光の中心へ、一直線に沈んでいった。
海はぽっかりと、直径500メートルほどの円を描き、
底まで丸見えになっていた。
そこには何もなかった。
船も、兵も、武器も、死体すら。
ただ、大地のように平坦な海底だけ。
そして光が収まると同時に、
海はまた音もなく閉じた。
まるで最初から何も起きなかったかのように。
切り立った岸壁の上に、数十人の侍が整列していた。
中心には鎧を付けぬ神官のような、
弓を持った数人の中心に「箱」があった。
祈りを終えた中央に立つ、神官風の人物。
赤でも金でもない、説明できない色を羽織った男は、
箱の前で、二拝四拍手一拝したのち、
跪いていた周りの神官が、その箱にさっと布をかけた。
黒い布中央には、金色の円形の紋章。
そこから花弁のような線が放射している。
海は何事もなかったように静まり返り、
一隻の船すら見えない水平線が広がっていた
——
- 1943年モンゴル -
城のように巨大な寺院の地下倉庫。
床にしたたる血痕。
縄。切られた馬具。
そして吊るされた男。
ロープが軋む音。
足は地面につかず、ゆっくり回転している。
薄明かりの中で、その男のシルエットが浮かび上がる。
シャツが破れたその男に、近づいてきた紳士が言った。
「お久しぶりですね。ジョーンズ博士」
黒いコート。丸眼鏡。ハットを深くかぶり片手には古文書の束。
「仁科博士?お前がなぜここにいる?」
仁科はインディを見上げながら続けた。
「あなたと同じですよ。
八咫鏡を調べてここに辿り着いた。
それだけのことです。」
インディは皮肉たっぷりに笑う。
「悪の枢軸国家で、新型爆弾作ろうとしているお前がか??
笑わせるな。
専門外の学問にご興味をお持ちとは意外だったよ。
あんたも“鏡の神話”なんて信じてないだろ。」
「もちろんです。
ただ私は全ての不思議な出来事に、科学的説明が出来ると思っているのです。
蒙古艦隊が跡形もなく消えた。
あなたもその古文書を探しにここへ来たのでしょう?」
「あれは嵐だよ。偶然だ」
「偶然が、あれほど”選択的に”船団だけを消しますかね?
それも2度も」
「何が言いたい」
「この封印が解ければ、世界が変わる。
マンハッタン計画も無力化です。
でも”ここ”にあなたがいた。
ジョーンズ博士。あなたほど厄介な”同業者”はそうはいませんよ。」
「同業者なら、降ろしてくれてもいいんじゃないか?」
ひきつった笑みを浮かべながら、インディは後ろ手に隠したナイフを動かしていた。
仁科の笑顔が消えた。
「だから、、あなたにはここで消えてもらう」
合図とともに、部下たちが近づいてきた。
次の瞬間、ロープに亀裂——
インディの身体が急落する。
直前でインディは足首の縄の緩みを利用し、片足をロープに引っかける。
落下と同時に身体を反転し、背後の柱にぶつかりながらも縄がねじ切れる!
ドサッ!
生きている。
すぐさま敵兵が一斉に剣を抜くが、
インディは砂を握り、敵の顔に投げつけ、
転がった槍を奪って、目の前の男を突き刺す。
砂煙が舞う。
下の馬具に装着されていたムチを拾い上げ、
仁科の古文書を持つ手をめがけて弾いた。
仁科は苦悶の表情を浮かべた瞬間、インディは仁科の手から古文書をもぎ取る。
古文書はちぎれ、半分になって仁科の手に残った。
砂埃の中を走り、
くたびれたフェルト帽子を、瞬時にかぶりながら階段を駆け上る。
地上に出れる!
次の瞬間、目の前に
大きな斧を持った男が立ちはだかった。
「またかよ、、、」
斧を振り回し、威嚇しながら近づいてくる男。
そして銃声が響いた。
男は斧を持ったまま、
ゆっくりと倒れ階段を転げ落ちていく。
「インディ!こっちだ!」
馬に乗った髭だらけの男が、銃を片手に迫ってきた。
「遅いぞ、サラー!」
モンゴルの平原を、二人を乗せた馬が駆けていく。
軍のジープに、兵士が乗り込んだときには
すでに馬の姿は見えなくなっていた。
97式軽機関銃の、
乾いた連続音だけが平原に響いていた。