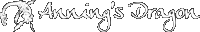インディ・ジョーンズ 剣山の秘宝〈第3話〉
次第に暗くなりはじめた夕方の花街。
華やかな夜に向かって、石畳を業者や舞妓が行きかう。
細い通りは迷路のように路地が交差している。
ときおり三味線の音が聞こえてくる。
インディはスーツケースを片手に、狭い石畳を歩いていた。
だがその背後に、規則的に響く靴音──2人、3人…いや4人。
うち1人は革靴。あとは重い靴音…
尾行だ。
インディは路地を曲がり、提灯の並ぶ細道に入る。
振り返らず、それでも気配だけが濃くなる。
そのとき、
「博士。こっちどすえ」
すっと横から白い手が、インディの腕をつかんだ。
振り向くと──
艶のある黒髪、真っ白な化粧、赤い唇。
若い芸妓が真っ直ぐな目線をインディに向けていた。
「……誰だ?」
「質問は後。いまは、ついてきて」
問い返す暇もなく、芸妓はインディを格子戸の奥へと引き込んだ。
一歩入ると、空気が変わった。
朱塗りの柱、金箔の屏風、香の匂い。
「博士、このままでは奴らに拉致されるわ。」
「拉致? 俺が?奴らとはなんなんだ??
その前にお前は誰だ?なぜ俺を知っている?」
芸妓は三味線の糸を急いで緩めながらさえぎる。
「奥にいて。Trust me。」
次の瞬間、ドンドンドン!と激しく表戸を叩く音。
そして怒号が続いた。
「開けろ!!」
芸妓はインディを奥の座に通し、後ろ手に障子戸を閉じた。
そしてすっと扇子を持ち、表戸を開く。
白いパナマハット。白いスーツの鋭い目の男が立っていた。
「ここに白人の男が来たはずだ」
「さあ…?どやろなあ。ここは一見(いちげん)さんお断りどすえ。今日は帰っとくれやす」
男は微笑む。だが目は笑っていない。
「また来る…」
芸妓は表戸を閉じた。
白いスーツの男が軽く手を上げると、
路地にとまっていたトラックの荷台から
旧日本軍の装備を身につけた武装兵が、ぞろぞろ降りてくる。
12人。機関銃など重武装をしている兵もいる。
ヘルメットに”3本足のカラス”の紋章があった。
日が落ち始めた、花街の暗がりに展開していく。
あまりの信じられない光景に、
通り行く人々は、映画の撮影か何かと思っているようだった。
「石室少佐、準備完了しました!」
「米田、塚森、突入しろ」
白スーツの石室は冷静にそう言い放ち、トラックの助手席に乗り込もうとしたときだった。
若い白人のアメリカのMP(ミリタリーポリス)がひとり近づいてきた。
距離50メートル。薄明りで顔は見えない。
だが、普通に歩いてくるところを見ると、平和ボケは米軍にも蔓延していたらしい。
「What are you doing!?ここで──」
ドンドン!
銃声。MPが倒れる。
兵士2名は、お茶屋の扉を蹴破り突入した。
玄関には先ほどの芸妓がいたが、
兵士たちは目もくれず銃を構え中へゆっくりと進む。
先行していた兵士が、インディのいる部屋の障子戸に近づいた。
芸妓の目つきが変わった。
後ろ側に続く兵士に音もなく近寄り、
背後から持っていた三味線の糸を瞬時に兵士の首にかけた。
三味線の棹(さお)をてこに一瞬で糸はピンと張り、
芸妓は素早く糸巻きをキリキリと回した。
兵士は即、失神。
背後の異変に、気がついた兵士が振り向く。
兵士の構えた100式機関短銃が、振り向きざまに乾いた連続音をいくつか放った瞬間、
兵士の背後から、障子戸が倒れ押し倒した。
倒れた障子ごと兵士に飛びついたインディは、兵士に馬乗りになり障子越しにムチで首を絞めた。
心拍数が一気に上がる。
頸椎を圧迫され、暴れる兵士が失神するまでの時間は長く感じられた。
「ジョーンズ博士!奴ら本気よ!」
「ここで死ぬのは趣味じゃない!」
突入した二人が、排除されたことを察知した石室は、即座に銃撃を指示した。
機関銃の音が鳴り響き、お茶屋は煌びやかな朱や金とともに飛び散る。
そこに二人はもういなかった。