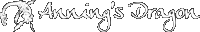インディ・ジョーンズ 剣山の秘宝〈第6話〉
- 仁徳天皇陵 外堀-
堀の水は、思ったより冷たかった。
澱んだ重い水は生臭く、
泳ぐたびに水を切る音は水面に吸い込まれていく。
真っ黒に染まった水面の先に、
茂みがかった岸がぼんやりと浮かんでいる。
文子はインディより、ずっと先を泳いでいた。
インディは悪態をつきながら、息荒くもがくように泳いでいく。
インディが、水を大量に含んだ重い服をひきずりながら、
斜面を、枝垂れた植物を頼りに登り切ったとき、
文子はすでに、ずぶ濡れの服を無言で絞り切っていた。
飲んだ水をゲホゲホと吐きながら、
ぜいぜいと息を上げるインディを、見下ろしながら文子は言った。
「……帰りのこと、考えてないでしょ」
GHQ統治下の、夜の仁徳天皇陵は、
警備も薄く、阻むものは、重く澱んだ水のみ。
文子の軽口に応えず、インディは思考をめぐらせる。
「真正面、ど真ん中に
後から作られた拝殿があるはずだ。」
「中央に?そこに入口がある?」
「そうだ。
古墳の入り口の坑道に、
後に神社が作られた例は日本中に多数ある。」
高々とした木々が生え、森と化した古墳を奥へ進んでいく。
周りは背丈より高い雑草で覆われていたが、
中央と思われる部分は、道のようにまっすぐ開けていた。
やはりどこか平面的で、
自然ではない“積み上げられた形”を感じさせる。
鞭で蜘蛛の巣を払いながら、進んでいくと、
暗闇の奥に、
巨大な鳥居が“置かれている”のが見えた。
「あったぞ…!」
インディは迷いなく、奥へ進んでいく。
文子は鳥居を通り過ぎる瞬間、ぺこりと頭を下げた。
地面はいつしか石畳となり、
しばらく進むと、
役割の違うように並んだ三つの拝殿が現れた。
「中央だ。
拝殿の奥に本殿がある。
……その先が、入口だ」
文子は、中央の拝殿に近づき、
二礼をし、柏手を打っている間に、
インディは土足のまま、どんどん社(やしろ)の中に入っていく。
「ちょっと!」
ムッとしながら、靴を脱ぎ、文子はついていく。
妙に磨かれている、本殿の床。
中央にご神体が祭られている、観音扉があった。
インディは迷わず開ける。
石で周りを囲われた”穴”が現れた。
「坑道だ」
インディは、低い声で言った。
人ひとり通れる通路から、
風が奥から吹いてくる。
奥は、暗い。
だが、真っ暗ではない。
どこからともなく、
光が「残っている」。
「やはり宇佐と同じだ。
入口は正面。
奥へ行くほど、下ってる」
「地下への通路、、
つまり、黄泉の国への階段ね」
拾っておいた松の棒に火をつけ、
さらに奥に進んだ。
傾斜は、ゆっくりだった。
だが、確実に地上から離れていく感覚がある。
足元で、何かが動いた。
インディが明かりを向けた、その先に——
それは、いた。
「……ヘビだ」
インディはあきらめと絶望の顔を浮かべた。
青大将が鎌首をもたげて二人を見ている。
インディが、腰のムチに手をかけようとすると
文子が言った。
「殺しちゃダメ。神の使いよ、多分…」
インディは蛇から目を逸らさず、
火を蛇に押し出しながら前に進む。
蛇は、道を塞がなかった。
まるで、
「そこは通っていい」
とでも言うように…
どれだけ歩いただろうか。
坑道はどんどん下り、
気がつくと、足元は水で濡れていた。
水かさは奥に行くにしたがって深くなり、
明かりをかざすと、奥は完全に水没している。
「行き止まりよ!」
「…また水かよ…」
インディは明かりで天井を照らす。
そこにうっすらと何かが彫ってある。
円形をかたどったもので、
汚れと風化で何が描いてあるのかは分からない。
左の壁には、半月状の何か、
右の壁には、長ぼそい何か。
「……左は船だ」
指でなぞる。
「右は、蛇……いや、龍に近い」
インディの言葉を聞いた文子は、誰に言うでもなく呟いた。
「……結界?」
水際に近づくほど、左側の壁は丸みを帯びていた。
削れたというより、撫でられ続けた形だった。
「これ……行くつもりなの?」
「左の壁を見ろ。水が深くなるにしたがって、
壁の一部が滑らかになってる。
片手を壁につけたまま、何人も通ってるってことだ」
「もし、息が続かなかったら?」
「だから、君はここに残れ。
帰ってこなかったら、助けに来てくれ。」
言い終わる前に、インディはざぶざぶと水に入っていった。
水は、思ったより冷たくなかった。
先ほどの堀の水と違い、透き通っているのを肌で感じる。
インディは壁に左手を添え、一歩ずつ進んでいく。
水は腰、胸、やがて喉元まで上がった。
帽子を脱ぎ、意を決して息を吸い込み水中の闇へ、
インディは没した。
冷たい水が、耳の奥に入り込む。
心臓の音だけが、やけに大きい。
壁は、確かに滑らかだった。
何度も、何度も、
人の手が撫でた跡がある。
指先で、石の継ぎ目をなぞる。
蛇行している。
闇。
距離が分からない。
時間も分からない。
肺が、
焼ける。
――終わらない。
まだ行ける。
まだだ。
胸が破裂しそうになった瞬間、
髪が、水面をとらえた。
インディは水面から顔を出し、
荒く息を吸い込んだ。
そこは、
石で囲われた小さな空間だった。
天井は低く、
水はここでせき止められている。
正面に、四角い巨大な箱がある。
――石棺だ。
視力が暗闇に慣れてくると、
石棺の向こうに何かがいる。気配が濃い。
それは、巨大な青大将だった。
先ほどのとは比べ物にならない大きさ。
鎌首を持ち上げてこちらを見ている。
インディは息をのんだ。
仁徳天皇陵は、支配の記念碑だ。
だから、この石棺は誰も眠っていない。
”権力の象徴”が入っているはず。
大蛇から目を逸らせないまま、インディは石棺の蓋に取りついた。
渾身の力を入れるまでもなく、石の蓋はゴリゴリと音を立てて動いた。
大蛇は微動だにしない。
まるで”そこ”に守るべきものがないかのように…
石棺の中には予想通り、ミイラは入っていない。
光を当てるまでもなかった。
それは、
自分から、わずかに光を返していた。
インディは、
濡れた手で、それに触れた。
菊型の円形、黒い石を磨いて作られたもの――
八咫鏡だ。
鏡の中心に、上段3文字、下段4文字、
合わせて2列のヘブライ語のような文字。
大蛇を睨みながら、インディは踵を返し、
来た道を戻った。
水をかき分け、必死に息をつなぎ、
ようやく水面から顔を出す。
「……文子!あったぞ!!」
声が、坑道に吸い込まれる。
返事はない。
インディは水から上がり、
帽子を被りながら、濡れたまま走った。
そのときだった――
足音が、
暗闇から、ゆっくりと近づいてくる。
乾いた、もたついた拍手の音と共に、
眼鏡の黒スーツの紳士が近づいてきた。
「お見事です。ジョーンズ博士。」
「…仁科!!!」
懐中電灯の光が、
インディの胸元を照らす。
その背後で、
文子が、両腕を押さえられて立っていた。
口元に血。
彼女の背後から、兵士が後ろ手に抑え込んでいる。
後ろには、将校姿の石室少佐が、数人の兵士を従えていた。
「お久しぶりですねぇ。
ありがとう、と言うべきでしょうな。
モンゴルでお会いして以降、あなたの動向を監視させ続けてきました。
私の目に狂いはなかった……さ、手を貸しましょう。」
仁科博士は、屈託なく片手を差し出し、インディに近づいていく。
八咫鏡は、懐中電灯の光を反射し、
一瞬、坑道を照らす。
文子がインディを見た。
ほんの一瞬、首を横に振る。
遅かった。
背後から、
銃床が振り下ろされる。
視界が、傾いた。
最後に見えたのは、
鏡に映った、自分の顔と、
その奥で、仁科の眼鏡が光っていた。